※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

電卓って左手で打たないと受からないの?
こんにちは、やぎです。
日商簿記1級を短期合格し、簿記の魅力を伝える発信をしています!
簿記を勉強すると、電卓を使用する頻度がとても高くなります。
しかし、簿記の学習過程で電卓の使用法について教えを受けることはなく、
基本的には独学で電卓の操作を覚えていく必要があります。
中には、「電卓は左手で打たないと合格できない」「見ないで打つのが当然」など、
様々な説が広まり、不安に思う方も多いのではないでしょうか?
はじめに結論から言うと、「右手で打っても」「見ながら打っても」簿記は合格することができます。
実際に、日商簿記1級や税理士試験(簿記論・財務諸表論)を合格した筆者の私は、
利き手である右手で、電卓を見ながら使用して結果を出しています。
「左手で」「見ないで」と言う説には、当然メリットがあるものの、
合格にはさほど左右しないと言うのが私の意見です。
そこで今回は、
- 「左手で」や「見ないで」が良いと言われる理由
- 「左手で」や「見ないで」が合格に必要ない理由
を紹介します。
この記事を最後まで読めば、簿記に合格するための電卓の使い方がわかります!

この記事では、「左手」=「利き手ではない方」という意味で書いているよ!
「左手で」や「見ないで」が良いと言われる理由

はじめに、どうして「左手で」や「見ないで」が推奨されているのか見ていきましょう。
主な理由は次のとおりです。
- 問題を解くスピードが早くなる
- 問題演習の効率が良くなる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
問題を解くスピードが早くなる
問題を解くスピードが早くなると言われています。
左手で電卓を打つことで、
「電卓を打ってから回答を記入するために、ペンに持ち替える時間」が短縮されます。
よって、結果的に問題を解くスピードが増すということです。
また、見ないで電卓を打つことで、
問題用紙→電卓→回答用紙・・と視線の移動が多くなります。
時間にするとコンマ何秒の世界ですが、
視線移動の積み重ねで回答スピードが落ちてしまうということです。
また、何度も視線を動かすことで、数字を見失ってしまうリスクもあります。
見ていた問題を改めて探すなどの時間もロスタイムになってしまうという訳です。

問題を解くスピードが早くなるなら、やった方が良い・・?

確かにそのとおり!
でも、時間にすると数秒。大事な観点が抜けてない?
問題演習の効率が良くなる

でも数秒とは言え、普段の勉強効率を考えたら早いに越したことはないよね?
確かに「左手で」「見ないで」電卓を打つことでロスタイムを無くすることで、
普段の問題演習の効率が良くなるとも言われています。
実際に、1問解くのに「5分かかる人」と「6分かかる人」がいるとすると、
同じ1時間の勉強時間で、
- 5分かかる人 →6問解ける
- 6分かかる人 →5問解ける
と、1問の演習差が出てしまいます。
それぞれ「6問解ける」「5問解ける」ので、1問も差が出ます。
100時間〜200時間も今後簿記を勉強していくとなると、大きな差になることは間違いありません。
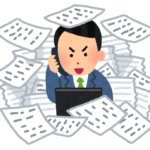
やっぱり大事じゃん・・!
今日から左手で打つ練習してみるよ!

ちょっと待って!!
確かに勉強効率の面でもメリットは大きいけど、
合格に直結することなのかな?

今度は「左手で」や「見ないで」がボクが必要ないと思っている理由を解説するよ!
「左手で」や「見ないで」が合格に必要ない理由

改めて結論ですが、簿記は「右手で打っても」「見ながら打っても」合格することができます。
先ほどまで、「左手で」や「見ないで」が良いと言われている理由を2点見てきました。
「左手で」や「見ないで」が良いと言われている理由(再掲)
- 問題を解くスピードが早くなる
- 問題演習の効率が良くなる
いずれも、その共通点は「スピードを重視している点」にあります。
もちろん、これも間違いではありません。
しかし、簿記試験で合格するために最も重視すべきことは、
「正確性」
にあります。
それは、簿記の学問には次の特性があるからです。
簿記の特性①:回答に対して計算量が多い
簿記は、回答に対する計算量が多い学問です。
例えば、日商簿記1級試験にもなると、
会社の株が動いたり、資産・負債が動いたり、外貨が出てきたり、、、、
散々カオスな出来事が起きていても「最終的に仕訳一本」で表されることもザラです。
簿記には部分点がありません。回答があっていたら正解、間違っていたら不正解です。
つまり、どれだけ理解していても、ミスをすれば理解できていないことと同様。
いかに「正確性」が重要か分かるかと思います。

確かに「この数字を出すために、こんなに計算したの(驚)」ってことあるよね。
簿記の特性②:数字が連動し合う
簿記は、一連の数字が連動し合う学問です。
「仕訳を答えよ」と言った問題だけであれば良いのですが、
簿記の原則は「貸借一致」 = つまり数字は常に表裏一体で動いていきます。
例えば、
減価償却費 100 / 減価償却累計額 100
と言う仕訳を間違えてしまったとします。
減価償却費(費用)の合計が合わなくなるので、結果的に利益が誤ることになります。
また、減価償却累計額(資産のマイナス)が合わなくなるので、資産の合計も誤りです。
このように1つ仕訳を間違えると、2個も3個も連動してミスが増えてしまうのです。
この点からも、簿記の「正確性」がいかに大事か分かるかと思います。

そういえば日商2級の工業簿記も、
第一問を間違えたら連動して、0点になることもあるよね。
以上のとおり、簿記で本当に大切なことは「正確性」です。
そのため、電卓の扱いについても、
「正確性」を重視して「どう扱うかを決める必要がある」と言うことです。
「正確性」を重視することで、
「左手で」「見ないで」が必要ない理由も次第に見えてきます。
その理由を詳しく見ていきましょう。
- 出題ボリュームが多くない
- ワンミスに対しての代償が大きい
- 無意識に正確なのは結局利き手
出題ボリュームが多くない
簿記試験は、出題される問題数のボリュームが多くありません。
資格試験はものによっては、完全解答を前提としていない試験もあります。
つまり「最後まで解ききれないので問題を取捨選択するのも必要だよ」といったものです。
こういった試験では1分1秒を争う必要があるのですが、簿記ではそんなことはありません。
簿記はある程度丁寧にやっても最後まで解き切れる試験です。
そのため、逆に「焦って何度も電卓を打ち直す」方が大事故になり得るものです。
そのため、時間をかけて電卓を打った方が合格に近づくと言えます。

解ききれないほどのボリュームでもないけど、
何度も打ち直す時間もない絶妙な試験なんだよね・・汗
ワンミスに対しての代償が大きい
簿記試験は、ワンミスに対しての代償が大きいです。
先ほども出た簿記の特徴でもありますね。
この問題を間違えたら、こちらの金額もズレる・・・といったことが簿記ではよくあります。
そのため、数秒のタイムロスには変えがたい正確性が求められます。

ボクは問題が最後まで終わってなくても、必ず一定時間を見直しに使っていたよ!
「最後に足掻いて取れる点数」<「凡ミスから連動して落とす点数をなくすこと」
例えば、運転免許試験のような一つ一つが独立した問題で構成されている試験であればスピードを重視すべきです。
しかし、簿記のような試験であれば時間をかけて電卓を打った方が合格に近づくと言えます。
無意識に正確なのは結局利き手
結局、無意識に正確なのは利き手です。
ATMやセキュリティ番号を打つときを思い浮かべてみてください。
日頃から、暗証番号を打つのは右手の方が多いのではないでしょうか?
本試験は、とてつもなく焦ります。
いくら練習しても結局土壇場で正確なのは、利き手なのです。
正確性が大事な試験においては、わざわざ左手で電卓を打つ必要がないという理由になり得ます。
Q & A

最後によく出る質問について答えていくよ!
「でも左手で打つのかっこよくない?後から変えれるかな?」
確かに左手の方が電卓に慣れている感じがして良いですよね。
ただ、どちらかというと「打つのが早い」ことの方が慣れている感じが出る気がします。
私も現在税務業を行っていますが、打つのが早い方が専門家イメージが付いて、信頼されやすいイメージですね。
また、後から左手に変えることも出来ます。
少し慣れの時間が必要ですが、おおよそ1〜2週間我慢すれば左手に変えることも出来ます。
そのため試験合格まではとりあえず右手、
実務をやることになったら左手で練習を始めるでも遅くないでしょう。
「1級受験生は左手が多い?」
やはり1級受験生は左手も多いです。でも、右手打ちも思った以上に多いです。
とはいえ私の経験上、「みんなが左手だから」「左手の方が早い」ではなく、
「自分で何度も試行錯誤した結果、左手が受かる可能性が高い」と強く信念を持っている人が勝ち上がっているイメージです。

ボクも何度も「左手」の方が良いと言われても曲げなかったよ。
でも、合格できたもんね!
まとめ:簿記は右手で打っても、見ながら打っても合格できる!
今回は、「左手」「見ないで」電卓を打っても合格できることを紹介しました。
そもそも「左手」「見ないで」が良いと言われる理由は、次のとおりです。
- 問題を解くスピードが早くなる
- 問題演習の効率が良くなる
これは間違いではありませんが、簿記で本当に大切なことは「正確性」です。
それは、
- 回答に対して計算量が多い
- 数字が連動し合う
と言う簿記の学問としての特徴があるためです。
正確性を重視した上で、「左手」「見ないで」が合格に必要ないと言える理由は次のとおりでした。
- 出題ボリュームが多くない
- ワンミスに対しての代償が大きい
- 無意識に正確なのは利き手
電卓の世界は意外と奥が深いです。
打ち方一つとっても考えることが多く、簿記の勉強過程では試行錯誤が必要になります。
このブログでは電卓に限らず、簿記に関する情報を発信しています。
簿記の魅力やおすすめ勉強法なども発信していますので、ぜひぜひご覧ください。

簿記は「正確性」!
以上、やぎでした!
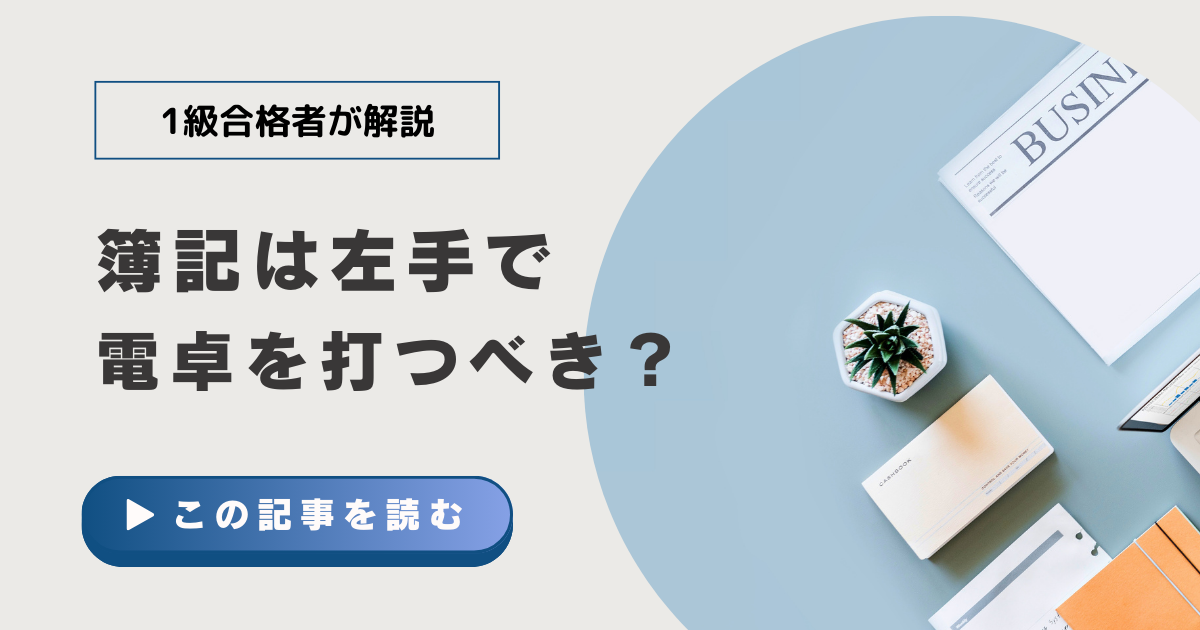
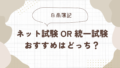

コメント